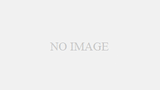子供が生まれたけど、知育には教材や本が絶対必要なのかな?
知育って良く聞くけど、よく分からない。
知育って何歳から始めるのがいいの、始めたいけど始め方が分からずなかなか始められない。
と思っているママやパパへ
今回は0歳時から始めるべき知育を看護師歴11年目、現在2児の母をしているせっかちなーすままが紹介していきたいと思います!
この記事を読んで分かること!
・知育とは知識を育ててる
・生まれたばかりの赤ちゃんからでも知育は始められる
・0歳児の一番の知育は愛情を沢山注ぐこと
・やってはいけない行動
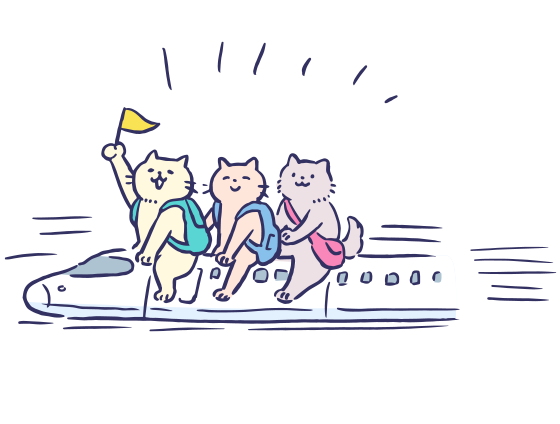
そもそも知育ってなに?
知育とは幼少期の子どもの知能や能力を育てる教育を指し、教育の基本「三育(さんいく)」(知育・徳育・体育)のひとつに数えられています。
三育を簡単にいうと、知育は知識を育てること、徳育とは道徳や倫理を育てるとこ、体育とは身体を育てる事をいい、これらすべてを育むことで身心ともに健全な成長を促すとされています。
その中でも今回注目したいのが知識を育てる「知育」です
知育を育てることで見につくもの!
・子供が自発的に考える力を身につける
・考える力や判断力を育てる
・社会性が身につく
・学習面で応用問題などに対応しやすくなる
などが言われています。

0歳児の一番の知育は愛情を沢山注ぐこと
赤ちゃんの脳は生まれてから6か月くらいまでに感覚領域の脳が育つと言われています。感覚領域とは見る、聞く、ぬくもりを感じるなどのことを言います。
知育を育てるためには脳や神経に刺激を与えていく必要があります。
そんな脳とか神経とか難しい事言われると、知育って難しそうなんてイメージを持つかもしれません。
でも実際はそんなこと全然なくて、0歳児へ一番の知育は愛情をいっぱい注いであげる事なんです。
沢山抱っこされたり、話しかけたり、本を読んであげたりして沢山コミュニケーションを取ることで感覚領域が発達し脳が育つための土台がしっかりと発達していきます。
感覚領域が発達することで感情豊かになり、成長していくに連れ、言葉、音、色、絵など様々なことに興味を持つようになります。
いつから始められる?
知育は生まれてすぐに始められます。
味覚・聴覚・嗅覚・視覚・触覚といった五感は、生まれたばかりではどの感覚もぼんやりしています。
新生児の視力は0.1以下とも言われ、光やシルエット程度して分からないと言われています。
生まれたばかりの赤ちゃんは明るいな、なんか聞こえるな程度の感覚です。
五感の中でも聴覚は一番発達していると言われており、お腹の中にいるときから音は聞こえていると言われています。
そのため生まれてすぐの赤ちゃんの感覚は、ぼんやりしていてパパやママの顔はしっかりとは見えていませんが、声は聞こえています。
沢山声をかけてコミュニケーションをとることで、ママやパパの声を認識し信頼関係や愛着形成生れどんどん脳に良い刺激がされます。

脳を発達を促すコツ
親子で楽しく遊ぶことが大事!
目を合わせて、スキンシップを沢山取って一緒に楽しむことが効果的とされています。
笑顔と愛情をもって接することが大切です。
スキンシップや一緒に遊ぶために、絵本やおもちゃを使うのはとてもいいと思います。
ですか、ここでの注意は絵本やおもちゃをただ与えただけになるのはNGです。
評価がいい知育のおもちゃを買って一人で遊ばせてもそれ脳への刺激は少なく知育とはいいません。それは親が満足してしまっているだけかもしれません。
大切なのは一緒に目を合わせて遊んで楽しむことです。
そうすることで子供の脳は刺激され大事な時期にしっかりと信頼関係や愛着形成がなされます。
やってはいけない行動

子供の前での暴言や夫婦間での喧嘩
生まれたばかりの赤ちゃんの五感はまだぼんやりしているとお伝えしましたが、ママやパパの不安や緊張感はしっかり伝わります。
ハーバード大学のある研究で両親の激しい喧嘩を見聞きして育つと子供の脳の視覚野は萎縮しIQや記憶力に影響がでることが分かっています。
この視覚野は視覚に直接完成する部分であり、視覚野が萎縮すると他人の表情を読み取りにくくなり対人関係でトラブルを抱えやすくなります。
産後はホルモンの影響でパパにイライラしたり、初めての子育てで思う様にいかず、ついきつい言葉を発したりしてしまう事もあるかもしれません。
それは誰が悪いというわけではありません。ですか子供の前ではなるべく喧嘩は避けるようにして、子供が寝た後やいないところで落ち着いて話しえるといいですね。
まとめ
知育とは知識を育てるための教育であり、0歳からでも始めることができます。
0歳からの知育とはママやパパから沢山愛情を注いでコミュニケーションをとり愛着形成や信頼関係を作ることで脳に沢山のいい刺激を与え発達します。
しかし、発達している脳にママやパパの喧嘩や暴言は悪い影響を与え、脳の萎縮に繋がり将来への発達に影響を及ぼす可能性があります。
ただずっと夫婦仲良くいるなんて正直難しく、夫婦の話合いは大切です。
そのため絶対喧嘩するなというのではなく、なるべくなら子供のいる前での喧嘩や言い争いは避ける様に心がけましょう。
そして少しでも多くの楽しい時間を夫婦一緒に子供と過ごしてみてください。